お使いのパソコンに搭載されている内蔵GPUと、後から追加した高性能な外付けGPU(グラフィックボード)を一緒に使えたら便利だと考えたことはありませんか。実は特定の条件下で、内蔵GPUと外付けGPUの併用は可能です。
この記事では、その具体的なメリットやデメリットについて詳しく解説します。さらに、ゲームのパフォーマンスに与える影響や、気になる消費電力の変化、RyzenやASRockといった特定の環境での設定方法、ノートパソコンで実現する際の注意点にも触れていきます。
内蔵GPUとグラボの切り替えに関する疑問から、おすすめの外付けGPUモデルの選び方まで、あなたの知りたい情報を網羅していますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 内蔵GPUと外付けGPUを併用するメリットとデメリット
- デスクトップやノートPCでの具体的な設定方法
- ゲームパフォーマンスや消費電力への影響
- 用途に合わせたおすすめの外付けGPUモデル
内蔵GPUと外付けGPUの併用で知るべきこと

- 併用によって得られるメリット
- 併用のデメリットと注意点
- 内蔵GPUグラボ併用による消費電力の変化
- 内蔵GPUグラボ併用はゲームに有効か
- 内蔵GPUとグラボの切り替え
併用によって得られるメリット
内蔵GPUと外付けGPUを併用することには、いくつかの明確なメリットがあります。最大の利点は、接続できるディスプレイの数を増やせることです。通常、グラフィックボードの出力端子の数で接続できるモニターの上限が決まりますが、マザーボード側の映像出力端子も活用することで、より多くの画面を同時に使用するマルチディスプレイ環境を容易に構築できます。
また、それぞれのGPUが持つ独自の機能を両立できる点も大きな魅力です。例えば、AMDの一部のAPU(内蔵GPU)に搭載されている動画再生支援機能「Fluid Motion」を使いながら、ゲームや重い処理は高性能なNVIDIAのGeForceに任せる、といった使い分けが可能になります。
さらに、アプリケーションごとに使用するGPUを割り当てることで、グラフィックボードへの負荷を分散させる効果も期待できます。ゲームは外付けGPU、ブラウザや動画再生は内蔵GPUといったように役割分担をさせることで、メインの作業へのリソースを集中させることができるのです。
併用の主なメリット
- グラフィックボードの出力端子数を超えてディスプレイを増設できる
- 内蔵GPUと外付けGPUの独自機能を同時に利用できる
- アプリケーションごとにGPUを割り当てて負荷を分散できる
併用のデメリットと注意点
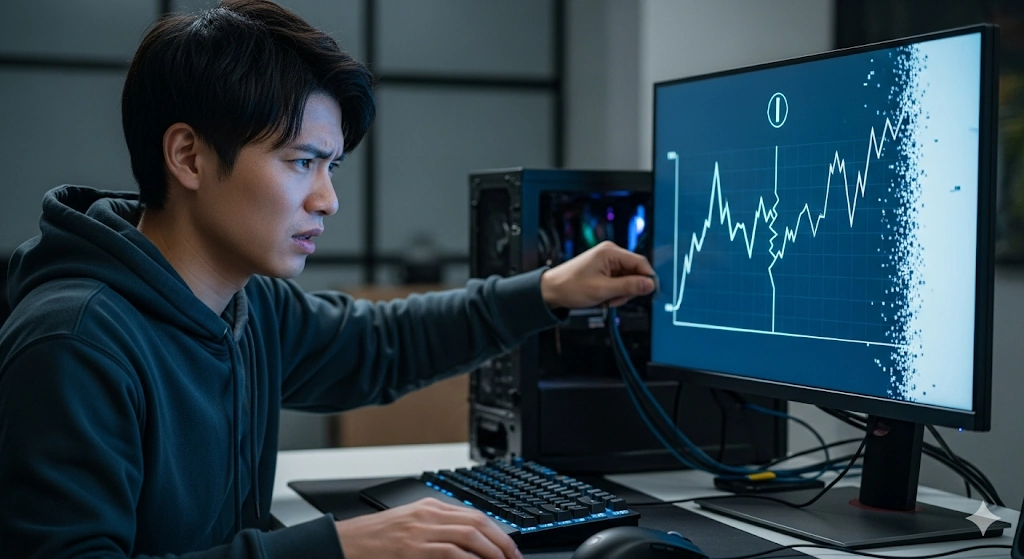
多くのメリットがある一方で、内蔵GPUと外付けGPUの併用には注意すべきデメリットも存在します。最も大きな問題は、システムが不安定になる可能性があることです。異なるメーカーのドライバが競合したり、相性問題が発生したりすることで、画面がちらつく、フリーズする、ブルースクリーンが発生するといった不具合に見舞われるケースがあります。
このようなトラブルは一般的ではない使い方であるがゆえに、インターネット上で解決策を見つけるのが難しい場合があります。トラブルシューティングには、イベントビューワーの確認やドライバのクリーンインストールなど、ある程度のPC知識が必要になるため、初心者にはハードルが高いかもしれません。
また、全てのパソコンで併用が可能なわけではありません。マザーボードのBIOS(UEFI)に、内蔵GPUを有効化するための設定項目が存在しない場合があります。特にメーカー製のPCでは、この設定がロックされていることが多く、併用自体が不可能です。自作PCやBTOパソコンであっても、事前にマザーボードの仕様を確認することが重要です。
併用時の主なデメリットと注意点
互換性の問題: 異なるGPUドライバの競合により、システムの不安定化や予期せぬエラーが発生する可能性があります。
情報の少なさ: トラブルが発生した際に、解決策を見つけるのが困難な場合があります。
ハードウェアの制約: マザーボードによっては、BIOSで併用を許可する設定項目自体が存在しないことがあります。
内蔵GPUグラボ併用による消費電力の変化
内蔵GPUと外付けGPUを併用すると、消費電力はどうなるのでしょうか。結論から言うと、基本的には消費電力は増加する傾向にあります。これは、これまで休止状態だった内蔵GPUも動作させることになるためです。特に、両方のGPUに負荷がかかるような使い方をすれば、その分だけ電力消費は大きくなります。
ただし、使い方によっては消費電力をわずかに抑えられる可能性も考えられます。例えば、普段のウェブブラウジングや動画視聴といった軽い作業を消費電力の少ない内蔵GPUに任せ、ゲームやクリエイティブ作業など高い性能が求められる場面でのみ高性能な外付けGPUを使用するという運用です。
これにより、常に外付けGPUをフル活用する場合と比較して、アイドル時や低負荷時の消費電力を低減できる可能性があります。しかし、その差はごくわずかであり、電気代を大幅に節約できるほどの効果は期待しない方がよいでしょう。消費電力の観点から併用を考えるよりも、前述したマルチディスプレイや機能の併用といったメリットを重視するのが現実的です。
消費電力に関する補足
外付けGPUは、それ自体が大きな電力を消費するパーツです。併用によって内蔵GPUが稼働する分の電力は上乗せされます。負荷分散による節電効果は限定的であるため、併用を検討する際は、十分な容量を持つ電源ユニットが搭載されているかを確認することも大切です。
内蔵GPUグラボ併用はゲームに有効か

「内蔵GPUと外付けGPUを併用すれば、ゲームのフレームレートが上がるのでは?」と期待する方もいるかもしれません。しかし、残念ながら、負荷分散によるゲームパフォーマンスの向上効果は、ほとんどの場合で限定的です。ベンチマークテストの結果を見ても、ゲーム以外のアプリケーションを内蔵GPUに割り当てた場合とそうでない場合で、スコアに大きな差は生まれないことがほとんどです。
これは、現代の外付けGPUが非常に高性能であるため、OSの操作や軽いアプリケーションの描画処理程度の負荷では、パフォーマンスにほとんど影響が出ないためです。ゲームのフレームレートを直接的に向上させる目的での併用は、あまり効果的とは言えません。
一方で、ゲーム配信のような使い方ではメリットがあります。例えば、OBSのような配信ソフトを内蔵GPUに割り当てることで、エンコード処理の負荷を内蔵GPUに任せることができます。これにより、外付けGPUはゲームの描画処理にリソースを集中させることができ、結果として配信中のフレームレート低下を抑える効果が期待できるのです。
つまり、ゲーム単体のパフォーマンス向上はあまり期待できませんが、ゲームをしながら別の作業(特に動画エンコードなど)を並行して行う場合には、負荷分散の恩恵を受けられる可能性がある、ということです。
内蔵GPUとグラボの切り替え
内蔵GPUと外付けGPU(グラボ)の切り替えは、使用しているPCのタイプによって仕組みが大きく異なります。
デスクトップPCの場合
デスクトップPCでは、基本的にモニターケーブルを接続した方のGPUが使用されます。マザーボードの映像出力端子に接続すれば内蔵GPUが、グラフィックボードの端子に接続すれば外付けGPUが有効になるというシンプルな仕組みです。そのため、使用するGPUを切り替えたい場合は、物理的にケーブルを差し替える必要があります。
ただし、グラフィックボードを増設すると、BIOS設定で内蔵GPUが自動的に無効化されることが一般的です。両方を同時に有効にするには、前述の通りBIOSで設定を変更する必要があります。
ノートPCの場合
一方、ノートPCでは、「NVIDIA Optimusテクノロジー」のような切り替え技術が採用されているモデルが多く存在します。これは、負荷に応じて内蔵GPUと外付けGPUを自動的に切り替えることで、パフォーマンスとバッテリー駆動時間の両立を図る仕組みです。
ユーザーが手動で切り替えることも可能で、NVIDIAコントロールパネルやWindowsのグラフィック設定から、アプリケーションごとにどちらのGPUを使用するかを優先的に指定できます。これにより、ケーブルの差し替えなしで、柔軟なGPUの使い分けが実現されています。
内蔵GPUと外付けGPUを併用する設定と実例

- Ryzenでの内蔵GPUグラボ併用方法
- ノートパソコンでの内蔵GPUグラボ併用
- おすすめの外付けGPUモデルを紹介
- 内蔵GPUと外付けGPUの併用について総括
Ryzenでの内蔵GPUグラボ併用方法
AMDのRyzenシリーズ、特にグラフィックス機能を内蔵した「G」シリーズのAPUと外付けGPUを併用する場合、特有の注意点と設定が存在します。主な目的は、APUが持つ動画再生支援機能「Fluid Motion」などを活用することです。
設定を成功させるための重要なポイントは、UEFI(BIOS)の「CSM (Compatibility Support Module)」設定です。この設定が有効(Enabled)になっていると、外付けGPUをプライマリに設定した際に内蔵GPUが認識されないという問題が発生することがあります。そのため、CSMは「Disabled(無効)」に設定することが強く推奨されます。
以下に、Ryzen APUと外付けGPUを併用するための推奨設定手順を示します。
- モニターケーブルを外付けグラフィックボードに接続します。
- UEFIを起動し、プライマリビデオアダプターを「Ext Graphics (PEG)」など、外付けGPUを優先する設定にします。
- 内蔵GPUを有効にするため、「iGPU Configuration」を「UMA_AUTO」などに設定します。
- 最も重要なポイントとして、「Boot」メニューなどにある「CSM」を「Disabled」に設定します。
- 設定を保存し、Windowsを起動後、AMDと外付けGPU(NVIDIAなど)の両方のドライバをインストールします。
CSM設定の重要性
CSMを有効にしたまま外付けGPUを優先設定にすると、Windowsのデバイスマネージャーで内蔵GPUが表示されず、併用に失敗する可能性が非常に高いです。このCSM設定は、併用時のトラブルで最もハマりやすいポイントなので、必ず確認してください。
ノートパソコンでの内蔵GPUグラボ併用

デスクトップPCとは異なり、ノートパソコンの多くは元々、内蔵GPUと外付けGPUを自動で切り替える機能(NVIDIA Optimusなど)を持っています。しかし、内蔵されている外付けGPUよりもさらに高性能なグラフィックス性能を求める場合、「eGPUボックス(外付けGPUボックス)」を利用するという選択肢があります。
eGPUボックスは、デスクトップ用のグラフィックボードを内蔵し、Thunderbolt 3またはThunderbolt 4という高速な規格でノートパソコンと接続する周辺機器です。これにより、グラフィックス性能が低いモバイルノートPCでも、デスクトップPCに匹敵するゲーミングやクリエイティブ性能を手に入れることができます。
ただし、導入にはいくつかのハードルがあります。
- コスト: eGPUボックス本体とグラフィックボードを別途購入する必要があり、高価です。
- 性能のボトルネック: Thunderbolt接続は高速ですが、デスクトップPCのPCI Expressに比べると帯域幅が狭いため、グラフィックボードの性能を100%引き出すことはできず、10~20%程度の性能低下が見られます。
- 安定性: ドライバの競合や接続の相性問題が発生しやすく、ブルースクリーンや認識不良など、トラブルシューティングに手間がかかることがあります。
手軽に性能を向上できる魔法の箱というよりは、知識と試行錯誤が求められる上級者向けのソリューションと言えるでしょう。
おすすめの外付けGPUモデルを紹介
外付けGPUボックスはいくつかのメーカーから発売されていますが、選択肢はそれほど多くありません。ここでは、実績と信頼性のある定番モデルを用途別にご紹介します。
定番で安心感のあるモデル:Razer Core X シリーズ
外付けGPUボックスと言えば、まず名前が挙がるのがRazer社の「Core X」シリーズです。多くのグラフィックボードに対応する広い内部スペースと、十分な電源容量(650W〜700W)を備えており、初心者から上級者まで幅広くおすすめできる定番製品です。
WindowsとMacの両方に対応している点も魅力。情報も比較的多いため、トラブルシューティングがしやすいという利点もあります。
省スペース性を重視するなら:SPARKLE TBX-240FU
よりコンパクトなモデルを求めるなら、SPARKLEの製品が選択肢に入ります。比較的小型のグラフィックボード向けですが、デスク上のスペースを圧迫しません。USBハブ機能や有線LANポートを備えているモデルもあり、ドッキングステーションとしての役割も兼ねることができます。
将来性と携帯性を求めるなら:GPD G1
最新のUSB4およびThunderbolt 4接続に対応し、将来性と携帯性の両方を重視したい方には「GPD G1」が最適です。このモデルは空のボックスではなく、高性能な「Radeon RX 7600M XT」を内蔵した世界最軽量級のポータブルeGPUです。約920gという軽さで持ち運びも容易なため、ノートPCの機動力を損ないません。
GPUがセットになったモデルに注意
一部の製品には、あらかじめグラフィックボードが内蔵された状態で販売されているものもあります。手軽に導入できるメリットはありますが、将来的にGPUの交換ができない、あるいは非常に困難な場合があるため注意が必要です。長期的な利用を考えるなら、中身を自由に入れ替えられるボックス単体のモデルをおすすめします。
これらのボックスに、自分の予算や目的に合ったグラフィックボード(例えば、コストパフォーマンスに優れたNVIDIA GeForce RTX 4060 Tiなど)を組み合わせるのが、最も一般的なスタイルとなります。
内蔵GPUと外付けGPUの併用について総括
今回の記事の内容をまとめます。
- 内蔵GPUと外付けGPUの併用は特定の条件下で可能
- 最大のメリットは接続できるディスプレイ数を増やせること
- それぞれのGPUが持つ独自機能を両立できる
- 負荷分散効果は期待できるがゲーム性能の向上は限定的
- デメリットとしてシステムが不安定になる可能性がある
- トラブル解決にはある程度のPC知識が必要になる
- すべてのマザーボードが併用に対応しているわけではない
- 併用設定にはBIOSまたはUEFIの変更が必須
- Ryzen APUとの併用ではCSMを無効にすることが重要
- デスクトップPCでのGPU切り替えはケーブルの差し替えが基本
- ノートPCではeGPUボックスを利用して高性能なGPUを増設できる
- eGPUはコストや性能ボトルネックの課題がある上級者向けの方法
- 外付けGPUはフルHDや4Kなど用途に合ったモデルを選ぶことが大切
- 導入前にはPCケースのサイズや電源容量の確認も忘れずに


