パソコンを使っていると、「ジー」や「キーン」といった耳障りな音が気になることがあります。こうした音の正体のひとつが、電源ユニットのコイル鳴きと呼ばれる現象です。特に静かな作業環境で作業している人にとっては、不快に感じることも少なくありません。
本記事では、「コイル鳴きとはどんな音なのか?」という基本から始まり、その原因や危険性、さらに具体的な対策や直し方まで詳しく解説していきます。場合によっては、電源ユニットの交換が必要になることもありますが、すべてのケースで修理が必要とは限りません。
「コイル鳴きは大丈夫なのか?」という不安を感じている方もいるかもしれません。この記事では、その疑問にも丁寧に答えながら、トラブルへの向き合い方を紹介します。自分でできる直し方から、再発を防ぐためのポイントまで、実用的な情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてください。
- コイル鳴きがどのような音かを理解できる
- 発生する原因や構造上の背景を把握できる
- 対処法や修理・交換の判断基準を学べる
- 再発防止や安全に使い続ける方法を知ることができる
電源ユニット コイル鳴きの原因と対策

- コイル鳴きとは どんな音かを解説
- コイル鳴きの原因は何か?
- コイル鳴きの危険性はあるのか?
- コイル鳴きは大丈夫なのか?判断基準
コイル鳴きとは どんな音かを解説
コイル鳴きとは、電子機器の内部から発せられる「ジー」「キーン」といった耳障りな音を指します。高音域のものが多く、人によってはかなり気になるレベルです。とくに静かな部屋や夜間の作業中には、想像以上に目立ちます。
この音は、通常の動作音とは明確に異なり、冷却ファンの風切り音やHDDの読み込み音とは区別がつきます。一定の周波数で継続的に鳴るケースもあれば、パソコンに負荷がかかったときだけ一時的に発生することもあります。
例えば、動画編集やゲームなどでパソコンの処理能力がフル稼働しているときに「キーン」という高周波のような音が聞こえると、それがコイル鳴きである可能性が高いです。一方、電源を入れた直後の低負荷時に「ジジジ……」といった低い音が出ることもあり、これもコイル鳴きの一種です。
音の種類は使っているパーツや構成によって変わりますが、共通する特徴として「電子部品由来の振動音であること」が挙げられます。もし耳につくような音が聞こえてきた場合、それがコイル鳴きかどうかの判断は、まずこのような音の特徴に注目してみると良いでしょう。
コイル鳴きの原因は何か?
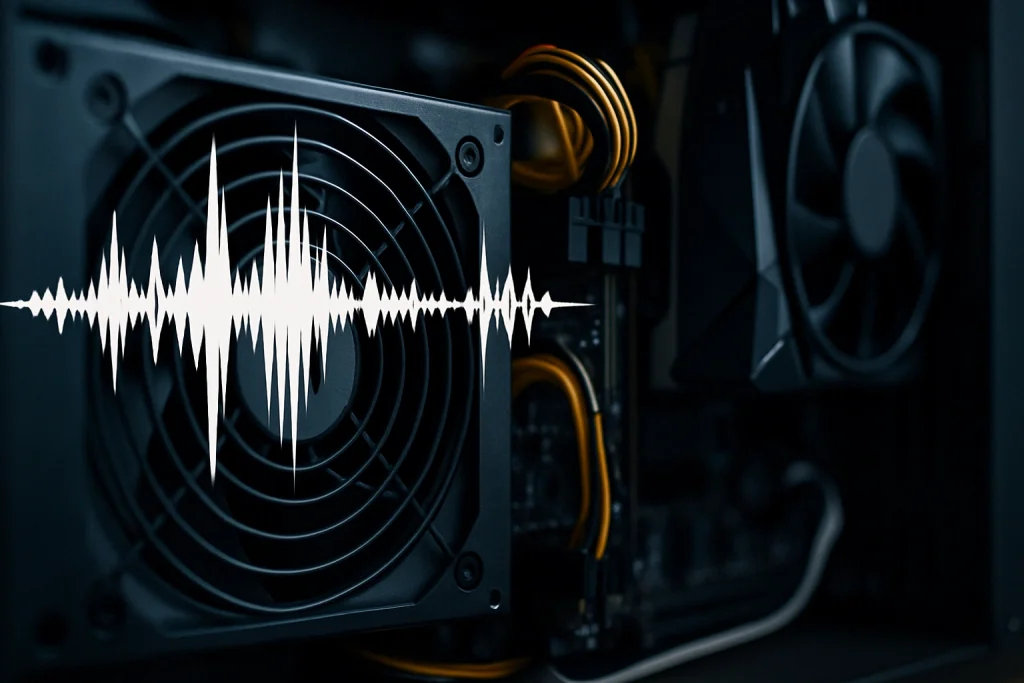
コイル鳴きの原因は、電子部品が電流の流れによって振動し、その振動が音として耳に届くことです。中でもトランスやインダクタといった「コイル系の部品」が共鳴を起こしやすいため、現象として“コイル鳴き”と呼ばれています。
この振動は、電気が流れる際に部品が物理的に共鳴し、それが空気を振動させて音になります。実際、部品の構造や取り付け方、絶縁材の有無、部品自体の劣化状態などが影響し、どれか1つでも条件が揃えばコイル鳴きが発生する可能性が高まります。
例えば、PCの構成を変更して新しいグラフィックボードを取り付けた際、それが旧式の電源ユニットと相性が悪いと、周波数のズレから共振が起きて鳴き出すことがあります。あるいは、防振対策が不十分な安価な電源ユニットを使用していると、初期から音が出ることもあります。
ここで注意しておきたいのは、コイル鳴きは必ずしも不良品で起こるわけではないということです。どれだけ品質の高い部品を使っていても、共振する条件が揃えば鳴いてしまうことがあるため、防ぎきれない部分もあります。
つまり、コイル鳴きの本質は「構造的な振動現象」であり、電子機器が正常に動作していても発生する可能性があるという点にあります。
コイル鳴きの危険性はあるのか?
コイル鳴きが直接的にパソコンの故障や火災を引き起こすリスクは、ほとんどありません。あくまで音の問題であり、多くの場合は動作に支障をきたすものではないため、過度に心配する必要はないとされています。
そもそも、コイル鳴きは電気を通す際に発生する微細な振動によるものです。これは仕様上避けられない物理現象であり、必ずしも「故障の兆候」とは限りません。高性能なグラフィックボードや電源ユニットであっても、特定の条件下で音が発生することがあります。
ただし、例外も存在します。例えば、異音の原因がコイルではなく、劣化したコンデンサやファンの故障だった場合、放置しておくと発熱やショートの原因になるおそれがあります。このようなケースでは、コイル鳴きと誤認したまま使用し続けると、深刻なトラブルを招く可能性があります。
このように、音の正体が何かを見極めることが、安全にパソコンを使うための第一歩になります。コイル鳴きだと断定できない場合は、無理に使い続けず、専門業者に確認してもらう選択も視野に入れるべきでしょう。
コイル鳴きは大丈夫なのか?判断基準
コイル鳴きが発生しても、すぐに修理や交換が必要なわけではありません。まずは音の大きさや頻度、パソコンの動作に影響が出ていないかを冷静に確認することが大切です。
実際、コイル鳴きは製品の仕様とされることも多く、メーカー保証の対象外になるケースが少なくありません。特に、購入直後から鳴っている場合は、設計上避けられないと判断されることもあります。したがって、「音がするから不良品」と即断するのは早計です。
判断基準としては、以下の点をチェックしてみてください。
・音が突然大きくなった、または異常な振動を感じる
・他の部品にも異常が見られる(発熱やリセットなど)
・静かな環境での作業が困難なほど音が気になる
こうした症状がないのであれば、使用を続けても問題はないと考えられます。一方、日常的に気になるほどの音でストレスを感じるようであれば、対策を検討する余地があります。
また、使用年数や構成の変更によってコイル鳴きが始まる場合もあるため、過去に問題がなかった機器でも注意を払っておくと安心です。繰り返しますが、「音が出る=危険」とは限らないため、まずは冷静に症状を見極めることが大切です。
電源ユニット コイル鳴きの直し方と交換方法

- コイル鳴きの対策と直し方の基本
- 自分でできる直し方と注意点
- 電源ユニットを交換する場合の目安
- コイル鳴きが再発するケースとは
コイル鳴きの対策と直し方の基本
コイル鳴きが気になる場合、まずは「共振を抑える」ことが基本的な対策になります。音の原因は電子部品の微細な振動なので、それを物理的に抑えることで静音化が期待できます。
最もよく使われるのが、ホットグルー(グルーガン)を使って振動している部品を基板に固定する方法です。ホットグルーは電気を通さず、乾くと固まり、部品の動きを物理的に制限することができます。100円ショップでも手に入るため、比較的手軽に試すことが可能です。
このほか、静音性に優れたPCケースに交換する、吸音材を貼り付ける、防振対策がしっかりした高品質の電源ユニットを選ぶといった方法も有効です。これらは部品そのものを修正するわけではありませんが、耳に届く音を軽減する効果があります。
ただし、こうした対策が必ずしも効果的とは限りません。部品の内部が原因の場合、外部からの補強では音を抑えきれないこともあるため、音が完全に消えるという期待は避けたほうが良いでしょう。また、分解を伴う作業は保証が無効になる場合もありますので、作業前に注意が必要です。
自分でできる直し方と注意点
自分でコイル鳴きを直す場合、いくつかの方法がありますが、安全性と作業環境に十分な配慮が必要です。無理をして壊してしまっては本末転倒なので、難しいと感じた時点で専門業者に依頼する判断も重要です。
もっとも手軽なのが、電源ユニットやマザーボードをPCに接続した状態で音の発生源を特定し、ホットグルーで対象の部品を固定する方法です。耳で音を聞き分けたり、ピンセットのような非導電素材で軽く押さえてみたりすると、どの部品が鳴っているのか判断しやすくなります。
ただし、この作業は電源が通電している状態で行うため、感電やショートの危険があります。また、パーツを誤って押しすぎると破損するリスクもあります。使用する工具や手の位置、作業台の絶縁対策まで注意を払う必要があります。
そして、製品を分解してしまうと、メーカー保証の対象外になることが多いです。特に、保証期間内であれば分解する前にサポートへ相談するのが無難です。
自分で修理することには達成感もありますが、安全性を確保しつつ、無理のない範囲で行うことが大前提です。難しいと感じる場合は、無理に手を出さず専門業者への依頼や電源ユニット自体の交換を検討するとよいでしょう。
電源ユニットを交換する場合の目安

電源ユニットを交換すべきかどうかは、音の大きさだけで判断するのではなく、パソコン全体の状態や使用年数、他の症状の有無を総合的に見ることが大切です。
まず、異音がひどく作業に支障が出るほどであれば、交換を検討する価値があります。特に静音性が求められる作業環境や、深夜に使用する機会が多い方にとっては、精神的なストレスにもつながります。
また、パソコンの動作が不安定になっている場合は要注意です。例えば、突然の再起動や起動の失敗が増えてきたときは、コイル鳴き以外にも電力供給の不安定さが影響している可能性があります。さらに、使用している電源ユニットが2年以上経過しているようであれば、経年劣化による性能低下も視野に入れるべきでしょう。
他にも、パソコンの構成をアップグレードして電力消費が増えた場合、既存の電源ユニットがそれに対応しきれず、結果的にノイズが発生することもあります。このようなケースでは、容量の大きな電源ユニットへ買い替えることで改善する可能性があります。
いずれにしても、音が気になるだけでなく、不安定な挙動や古さが重なる場合は、交換を検討する一つの節目と考えると良いでしょう。
コイル鳴きが再発するケースとは
コイル鳴きを一度対策しても、条件が変われば再び音が出てしまうことがあります。これは構造上の問題ではなく、使用環境やパソコン構成の変化によって再発するケースがあるためです。
たとえば、新しいグラフィックボードやCPUを導入した後に、電源ユニットとの相性が悪くなり、再び鳴き始めることがあります。このような場合、部品同士の周波数の共振が変化し、それが音となって現れるのです。
さらに、季節による室温の変化や、長時間の使用による内部パーツの温度上昇も再発の引き金になることがあります。熱によって基板や部品がわずかに歪むことで、共振の起こるポイントが変わってしまうのです。
前述の通り、ホットグルーなどで一時的に振動を抑える対策を施した場合でも、別の部位が鳴き出すことも珍しくありません。特に電源ユニットの内部は複雑な構造のため、すべての鳴きの要因を一度に取り除くのは難しいのが現実です。
このため、静音を重視した設計の電源ユニットに買い替えることで、ある程度再発リスクを減らすことはできますが、「完全にゼロにする」ことは難しいと理解しておくと良いでしょう。
電源ユニット コイル鳴きの原因から対策までの総まとめ
今回の記事の内容をまとめます。
- コイル鳴きは「ジー」「キーン」といった高周波の電子音
- 静かな環境ほどコイル鳴きが目立ちやすい
- 音はパソコンの負荷状況に応じて変化する
- 主な原因は電子部品の共振による振動音
- トランスやインダクタが特に鳴きやすい傾向がある
- 部品の劣化や取り付けの甘さも原因になり得る
- 高品質なパーツでも鳴くことがあるため完全防止は難しい
- コイル鳴きは基本的に故障や火災の原因にはならない
- 異音の正体が他の不具合の可能性もあるため注意が必要
- 音が急激に大きくなった場合は点検が必要
- ホットグルーで部品の振動を抑える対策が一般的
- 静音ケースや吸音材による音の軽減も効果がある
- 分解しての対策は保証対象外となるリスクがある
- パソコン構成の変更後に再発するケースがある
- 電源ユニットの経年劣化や出力不足も交換の目安となる


